ベトナム市場調査:ポスト中国の有力候補!製造業向け投資優遇&3大成長セクター
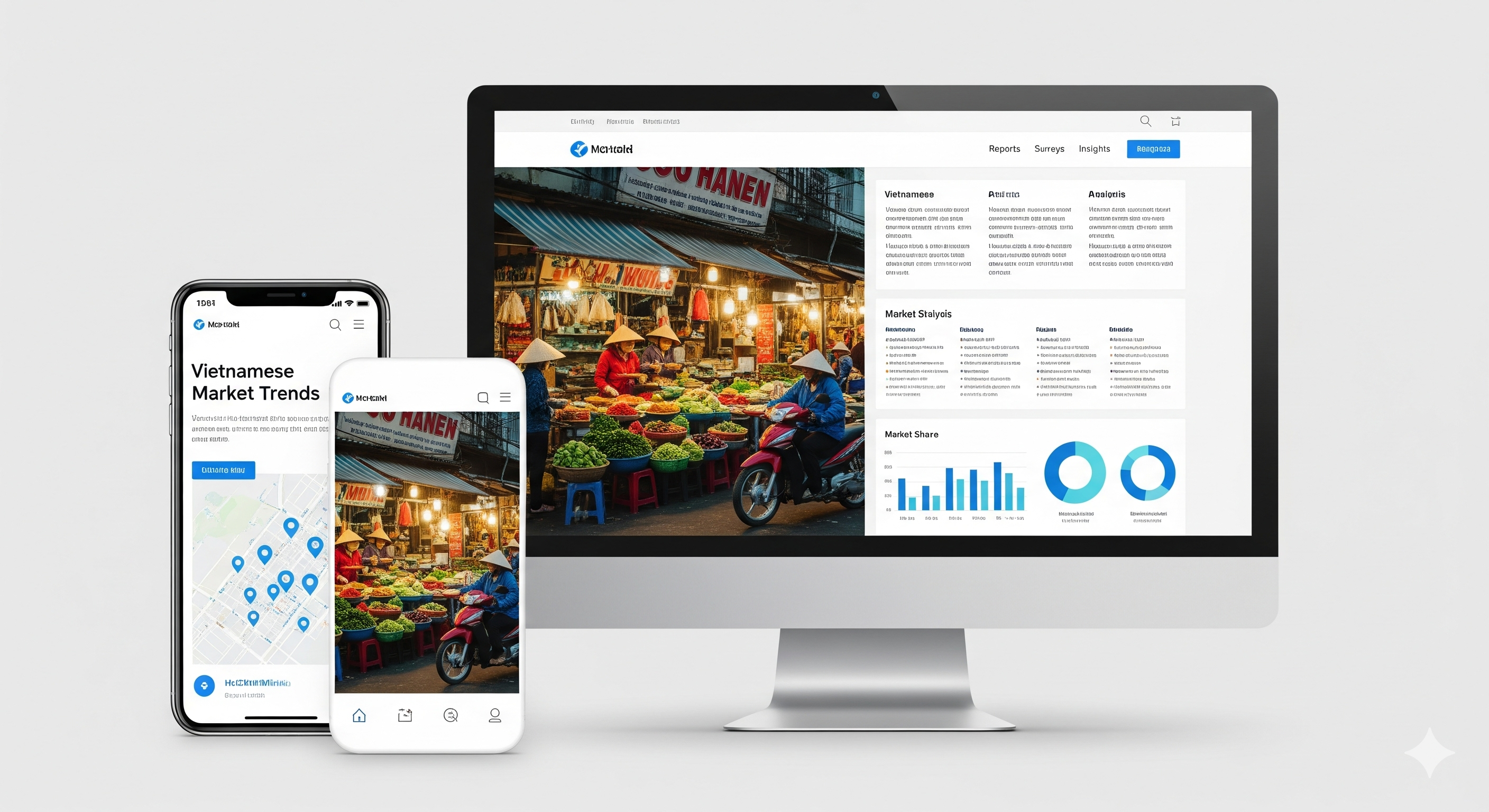
なぜ今、ベトナム市場が「チャイナ・プラスワン」の筆頭なのか?
米中対立の激化や中国国内の人件費高騰を背景に、多くのグローバル企業が生産拠点を中国から他国へ移す「チャイナ・プラスワン」の動きを加速させています。その最有力候補として、今、世界中から熱い視線が注がれているのがベトナムです。
約1億人の人口、安定した政治体制、そして5%を超える高い経済成長率。これらの魅力的な要素に加え、政府主導の積極的な外資誘致策が、海外からの投資を強力に後押ししています。しかし、その輝かしい成長性の裏には、インフラ問題や法制度の複雑さといった、進出企業が直面する現実的な課題も少なくありません。
本記事では、海外進出を検討するBtoB・製造業の経営者様に向けて、ベトナム市場の「ポテンシャル」と「リスク」を多角的に分析し、成功への道筋を具体的に解説します。
巨大市場のポテンシャル:成長を牽引する3つのエンジン
ベトナムの力強い成長は、3つの強力なエンジンによって支えられています。
エンジン1:豊富な若年人口と「人口ボーナス」
ベトナム最大の魅力は、その若く豊富な労働力です。インドネシア市場調査でもありましたが、ベトナムでも同じく、総人口約1億人のうち、平均年齢(中央値)は約32.8歳。これは、生産年齢人口がそれ以外の従属年齢人口(年少者、高齢者)を大きく上回る「人口ボーナス期」の真っ只中にあることを意味します。この豊富な労働力が、経済成長の源泉となっています。また、勤勉で手先が器用な国民性は、高品質なモノづくりを目指す製造業にとって大きなアドバンテージです。
年齢中央値の国際比較 (2025年)
ベトナムの年齢中央値は世界平均よりわずかに高いものの、日本に比べると約17歳も若く、豊富な労働力が経済を支えています。
エンジン2:拡大する中間層とデジタル消費
経済成長に伴い、ベトナムでは中間層・富裕層が急速に拡大しています。彼らの旺盛な消費意欲は、国内市場を活性化させる大きな力です。特に、スマートフォンの普及率は95%を超え、若者を中心にSNSやEコマースの利用が爆発的に増加。物理的な小売インフラが整う前にデジタル化が先行する「リープフロッグ現象」が起きており、デジタルマーケティングの重要性が極めて高くなっています。
エンジン3:積極的な外資誘致と自由貿易ネットワーク
ベトナム政府は、外資誘致を国策の柱と位置づけています。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)や東アジア地域包括的経済連携(RCEP)など、数多くの自由貿易協定(FTA)を締結。この広範なFTAネットワークにより、ベトナムを生産拠点とすることで、世界各国へ低い関税で製品を輸出できるという大きなメリットが生まれています。
【製造業・BtoB向け】ベトナムの未来を創る3大成長セクター
ベトナム政府は、単なる労働集約型の生産拠点からの脱却を目指し、高付加価値産業の育成に力を入れています。特に注目すべき3つのセクターをご紹介します。
セクター1:電子産業・EVサプライチェーン
SamsungやIntelといった世界的な大手ハイテク企業が大規模な生産拠点を構えるなど、ベトナムは電子機器・部品の一大集積地となりつつあります。近年では、国産EVメーカー「VinFast」の台頭もあり、EV(電気自動車)関連の部品や素材、バッテリー技術など、巨大なサプライチェーンでのビジネスチャンスが広がっています。
セクター2:再生可能エネルギー
急速な経済発展に伴う電力需要の増加は、ベトナムにとって喫緊の課題です。政府は「第8次国家電力開発計画(PDP8)」を策定し、2050年までのカーボンニュートラル達成を目標に掲げました。これにより、太陽光発電や洋上風力発電プロジェクトへの国内外からの投資が活発化しており、関連する設備や技術を持つ日本企業にとって大きな追い風となっています。
セクター3:IT・DX(デジタルトランスフォーメーション)
質の高いIT人材が豊富で、人件費も比較的安いことから、ベトナムはソフトウェア開発のオフショア拠点として世界的な評価を得ています。さらに、国内の製造業やサービス業でもDX化のニーズが急速に高まっており、生産管理システム、クラウドサービス、サイバーセキュリティなど、日本の先進的なITソリューションが求められています。
【製造業必見】海外投資を後押しする投資優遇制度
ベトナム政府は、特にハイテク分野や裾野産業(部品・素材産業)を対象に、魅力的な投資優遇制度を設けています。
- 法人税の優遇措置: 新規投資プロジェクトに対し、最初の数年間が免税、その後の一定期間が減税となる「4年免税・9年半減」などの措置があります。特にハイテク分野や経済的に困難な地域への投資は、より手厚い優遇が適用されます。
- 工業団地(IZ)・経済区(EZ): 国内各所に整備された工業団地(IZ)や経済区(EZ)に入居する企業は、法人税優遇に加え、土地使用料の減免や、ワンストップでの行政サービスといった恩恵を受けられます。
- 輸入関税の免除: 工場建設のための機械設備や、日本国内では生産されていない原材料・部品などの輸入関税が免除される制度があります。
これらの制度は適用要件が細かく規定されているため、進出を検討する際は会計事務所などの専門家と連携し、自社の事業がどの優遇措置に該当するかを事前に確認することが不可欠です。
進出で失敗しないための現実的なリスクと対策
大きなポテンシャルを秘めるベトナム市場ですが、見過ごせないリスクも存在します。
- 人件費の高騰と人材獲得競争: 近年、最低賃金は年々上昇しており、特に都市部では優秀な人材の獲得競争が激化しています。給与水準だけでなく、福利厚生やキャリアパスを整備し、従業員の定着率を高める努力が求められます。
- 電力不足とインフラ問題: 経済成長にインフラ整備が追いついておらず、特に乾季には計画停電が頻発するなど、電力不足が製造業の安定稼働を脅かす大きなリスクとなっています。自家発電設備の導入など、BCP(事業継続計画)の観点からの対策が必要です。
- 法制度・行政手続きの複雑さ: 法律の解釈や運用が担当者によって異なるなど、行政手続きの不透明性(通称:レッドテープ)が指摘されています。信頼できる現地のコンサルタントや法律事務所との連携が、事業をスムーズに進める上で欠かせません。
- 低い国内部品調達率: ベトナムの裾野産業はまだ発展途上にあり、多くの部品や原材料を中国などからの輸入に頼っているのが現状です。そのため、サプライチェーンの寸断リスクには常に注意を払う必要があります。
ベトナム進出前に知るべき特徴的な商習慣
1. 人間関係(Quan He/クアンヘ)を何よりも重視する
ベトナムのビジネスにおいて最も重要な概念が「Quan He(クアンヘ)」です。これは日本語の「コネ」や「人脈」に近いですが、それ以上に個人的な信頼関係や恩義といったウェットなニュアンスを強く含みます。
特徴
- 「誰が」を重視: 「どの会社の担当者か」ということよりも、「個人として信頼できるか」が取引の前提条件になることが非常に多いです。
- 時間をかける: 本題に入る前に、雑談や会食を通じて何度も顔を合わせ、相手の人間性を理解しようとします。このプロセスを省略してビジネスの話を急ぐと、不信感を抱かれる可能性があります。
- 公私の区別が曖昧: ビジネスパートナーとプライベートな友人としての関係が重なることがよくあります。週末にゴルフに誘われたり、家族のイベントに招待されたりすることも、関係構築の一環と捉えられています。
日本企業が留意すべき点
担当者が変わると、会社間の取引であっても関係がリセットされ、振り出しに戻ることがあり得ます。後任への引き継ぎは、業務内容だけでなく人間関係の紹介も含めて丁寧に行う必要があります。
2. トップダウンと集団主義が共存する意思決定
ベトナム企業の意思決定プロセスは、日本人から見ると少し複雑に映ることがあります。
特徴
- 最終決定はトップダウン: 最終的な権限は社長や会長など、組織のトップに集中しているケースがほとんどです。現場担当者との交渉で合意しても、最後の最後でトップの一声で覆ることは珍しくありません。
- 根回しの重要性: 一方で、トップに話が上がる前に、関係部署のキーマンたちの非公式な同意を取り付けておくことが重要になります。これは日本の「根回し」に似ていますが、より非公式で人間関係に依存する側面が強いです。
- 「検討します」の意味: 担当者がその場で即決することは稀です。「持ち帰って検討します」という言葉は、単なる社交辞令ではなく、本当に関係者と調整し、上司の承認を得るための時間が必要であることを意味します。
日本企業が留意すべき点
交渉相手の役職だけでなく、組織内での実質的な影響力を持つキーパーソンを見極めることが重要です。また、意思決定には時間がかかることを前提に、余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。
3. 「メンツ(the dien/ザジェン)」を重んじる文化
ベトナム人は、他人の前で自尊心や社会的体面を傷つけられることを極端に嫌います。これを「メンツを失う」と言い、ビジネス上のコミュニケーションでは最大限の配慮が必要です。
特徴
- 人前での叱責は厳禁: 部下や取引先の問題点を指摘する際は、絶対に人前で行ってはいけません。必ず1対1のプライベートな場で、相手の立場を尊重しながら穏やかに伝える必要があります。
- 間接的な表現を好む: 直接的な「No」という表現を避け、「難しいかもしれません」「少し問題があります」といった婉曲的な言い方をすることが多いです。相手のメンツを潰さないための配慮です。
- 過剰に見えるほどの感謝: 小さな親切に対しても、大げさなくらいに感謝の意を示すことがあります。これも相手のメンツを立てるための重要なコミュニケーションです。
日本企業が留意すべき点
交渉の場で相手を問い詰めたり、論理的に追い込んだりするスタイルは逆効果です。相手のメンツを立てながら、こちらの要望を少しずつ伝えていく忍耐強さが求められます。
4. 会食や贈答の重要性
前述の「Quan He」を育む上で、会食(飲み会)や贈り物は欠かせない要素です。
特徴
- 頻繁な会食: ビジネスディナーやランチは頻繁に行われ、重要な商談が会食の場でまとまることも少なくありません。お酒(ビールやウォッカ)を酌み交わし、打ち解けることが関係構築の近道とされています。
- 贈り物(ギフト): テト(旧正月)前などの季節の挨拶や、契約成立時などに贈り物を交換する習慣があります。高価すぎるものは賄賂と見なされるリスクがあるため、日本の菓子折りや自社のノベルティグッズなどが無難です。
- 割り勘はしない: 基本的に招待した側が全額支払います。相手に支払いをさせると「メンツを潰された」と感じさせてしまう可能性があります。
日本企業が留意すべき点
会食の誘いには積極的に応じることが推奨されます。お酒が飲めない場合でも、その場に参加し、楽しむ姿勢を見せることが大切です。
5. 時間や契約に対する柔軟な考え方
日本人の時間や契約に対する厳格な感覚とは、少し異なる側面があります。
特徴
- 時間への柔軟性: 「ベトナム時間」という言葉があるように、約束の時間に少し遅れることに対して寛容な傾向があります(特にプライベート)。ただし、外国人とのビジネスアポイントメントでは時間厳守が基本とされつつあります。
- 契約は「ゴール」ではなく「スタート」: 日本では契約書へのサインが取引のゴールと見なされますが、ベトナムでは「良好な関係のスタート」と捉える傾向があります。契約締結後も、状況の変化に応じて条件の再交渉を求めてくることもあり得ます。
日本企業が留意すべき点
納期やスケジュール管理は、日本基準で考えるのではなく、定期的に進捗を確認し、遅延の可能性を常に念頭に置いたリスク管理が必要です。契約内容についても、継続的に良好な関係を維持する努力が求められます。
まとめ:ベトナム市場成功の鍵は「変化への適応力」
ベトナムは、計り知れないほどのポテンシャルと、無視できない課題が共存する、ダイナミックな市場です。法制度や市場トレンドの変化は非常に速く、かつて有効だった戦略がすぐに陳腐化することも珍しくありません。
この市場で成功を収めるために最も重要なのは、「固定観念を捨て、現地の変化に迅速かつ柔軟に適応していく姿勢」です。そして、複雑な商習慣や行政手続きを乗り越えるための「信頼できる現地パートナー」を見つけること、そして常に最新の情報を収集し続ける「学習意欲」が、その成否を分けることになるでしょう。
引用・参照元一覧
一覧を見る
世界銀行:The World Bank in Vietnam
国際通貨基金(IMF):Vietnam at a Glance
ベトナム統計総局 (General Statistics Office of Vietnam)
外務省:ベトナム基礎データ
貴社のベトナム戦略、専門家と共に描きませんか?
「チャイナ・プラスワンの最適地は?」「自社製品に最適な進出戦略を知りたい」
ZENKENでは、これまで8,000件以上のWebマーケティングを支援してきた実績を元に、貴社に最適な海外進出戦略をご提案します。
